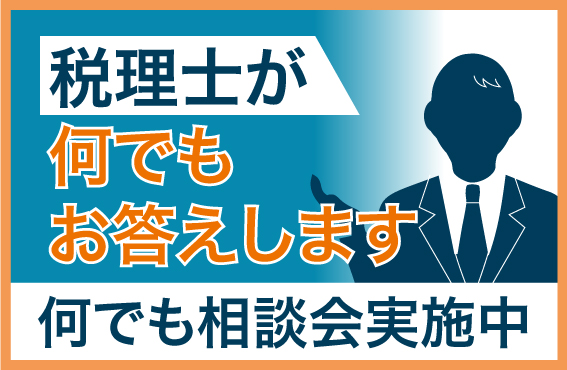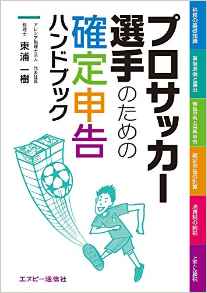会社設立:会社設立費用は経費になるの?経営を考えている人必見!

将来会社を設立したいと考えている人はたくさんいるのではないでしょうか。
会社を設立する際にはたくさんの費用が発生します。
設立時の費用は経費になるのかなど、その会社の費用をどのように会計処理するかについて知っている人は少ないと思います。
そこで今回は会社設立の費用の会計処理についてご紹介します。
会社の設立の流れ
それではまずは会社設立の流れについてご紹介します。
会社を設立する際にはまず、定款を作成します。
定款とは会社の憲法と呼ばれているもので会社の目的や本店所在地などを書きます。
その後その定款を公証人役場にて「認証」します。
定款の認証が終わりましたら、今度は法務局にて会社の設立登記をします。
ここで初めて会社が誕生したことになります。
その後は税務署や社会保険事務所などに届け出を出して晴れて、開業という形になり事業をスタートすることができます。
会社設立に係る費用
ではさきほどの会社設立の流れの中でいったいいつ費用が発生するのでしょうか。
まずは定款を作成する際に、自分で作るのか、司法書士や行政書士などの専門家に依頼するのかによって、変わります。
専門家に依頼すると当然お金がかかります。
次に定款の「認証」をする際に、費用がかかります。
電子認証もできますが、道具をそろえるのにお金と手間がかかります。
また、登記の際にも登録免許税が発生するので費用がかかります。
このように流れのいたるところでお金がかかることが分かります。
費用の会計処理
では最後に費用の処理の仕方についてご紹介します。
まず会社設立にかかった費用は、会社ができる前のことですが、会社の経費とすることができます。
この会社の設立にかかった費用は、「創立費」として一旦資産として計上をします。
資産に計上すると、その年に一括で落とすことができません。
ただし、法人税法上は5年以内に償却するのであれば、償却方法は「任意」となっていますので、その年に一括で落とすことも可能です。
一旦資産に計上して、また一括で落とすという少し手間がかかります。
その他に似たような科目で「開業費」というものがあります。
これは会社を設立後に、営業が開始するまでにかかった費用のことです。
賃借料、広告宣伝費、水道光熱費、通信費などです。
この処理の仕方も創業費と同じで一旦資産に計上し、5年の任意償却で落とせます。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
今回は会社設立に係る費用とその会計処理についてご紹介しました。
創業費は「会社設立前にかかった費用」で開業費は「会社設立後に営業日前までにかかった費用」だということを間違えやすいので覚えておいて下さい。
このように、会社設立を考えている人は、経費を賢く使うことによりかなりの節税効果になることを覚えておきましょう。
最新情報
- 2018.12.13
- 源泉徴収票のしくみと所得税の計算方法について解説します
- 2018.12.13
- 確定申告の疑問?青色申告と白色申告の違いについて解説します
- 2018.02.02
- 節税のポイント・平成29年度の確定申告代行します
- 2018.02.02
- 青色専従者控除について 平成29年度の確定申告代行します
- 2018.02.02
- エステ店の確定申告代行ならアレシア税理士法人まで